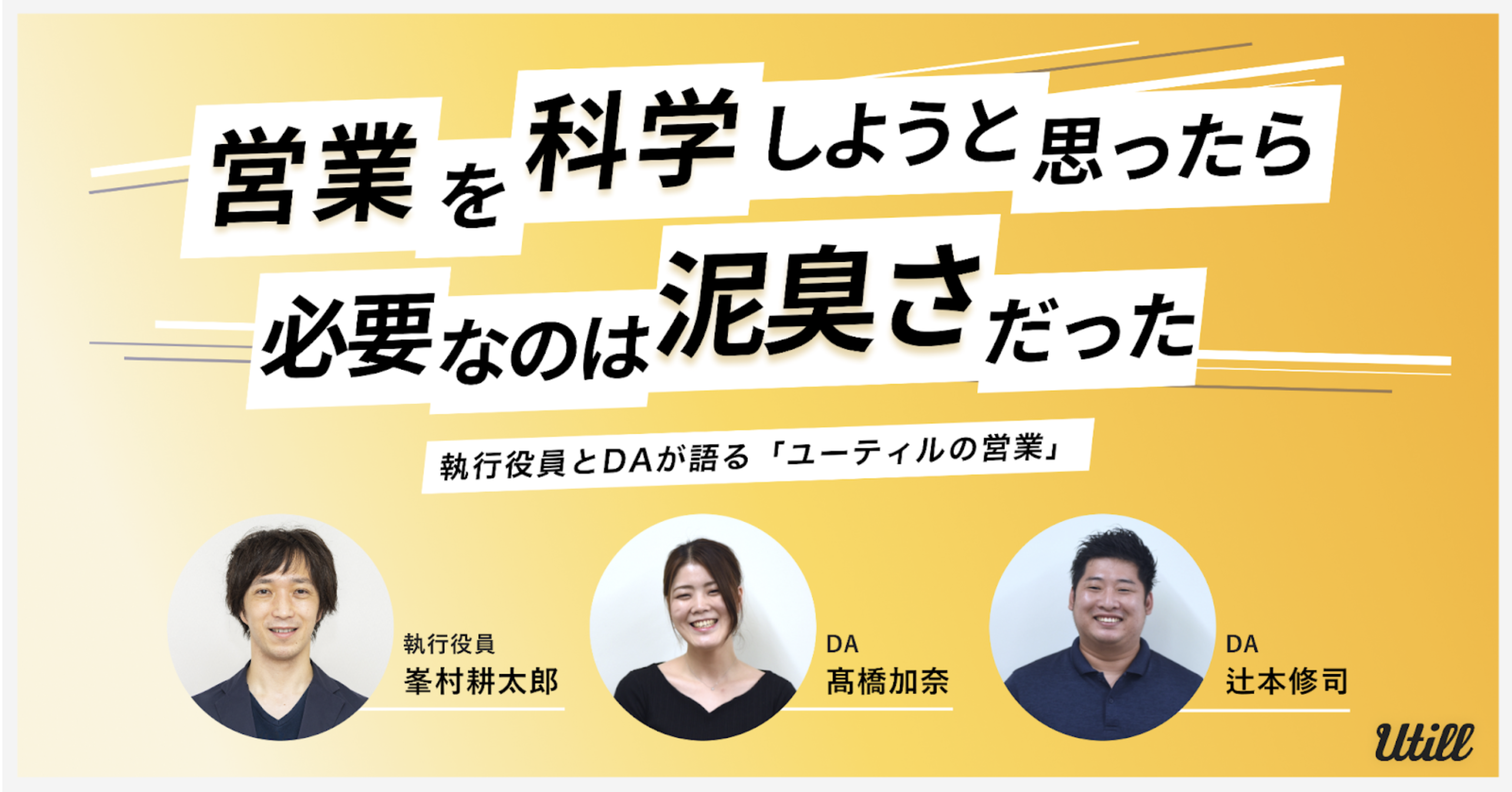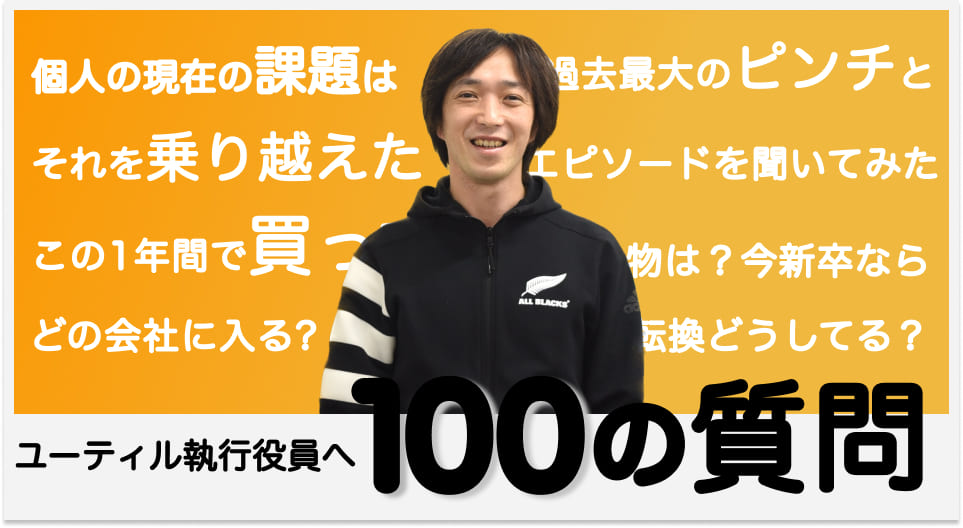トップセールスのトークを型化し、高い受注率を叩き出す。できるくん代表が描く、中小企業のデジタル革命

営業のプロとして数々の組織を成功に導いてきた小林祥太さん。アリババ、クックパッド、ココナラといった名だたる企業での経験を経て、自らもSaaS企業を立ち上げ、その後2024年にM&Aでユーティルグループに参画。
現在は株式会社ユーティルの執行役員兼株式会社できるくんの代表取締役として、できるくん事業の立ち上げを牽引しています。この記事では、BPaaSという新たな概念で日本中の中小企業のポテンシャル開放に挑む、小林さんのキャリア変遷や情熱、哲学に迫ります。
小林 祥太(Shota Kobayashi)
創業期のgroovesに入社以降、アリババ日本法人、クックパッド、ココナラで営業組織の立ち上げ、マネジメント、新規事業の立ち上げなどを経験。2017年、株式会社Onionの取締役COOとしてSalestech SaaSを立ち上げ500社以上の営業支援を経て2021年独立。2024年、M&Aによりユーティルグループにジョイン。株式会社ユーティルの執行役員 兼 株式会社できるくんの代表取締役に就任。
リーマンショックで学んだ、市場選定の重要性
ーー小林さんがこれまで歩んできたキャリアについて教えてください。
1社目は、学生時代のアルバイト先だった人材系ベンチャーに入社しました。大学4年の時には既にフルタイムで働いていたので、形式上は2008年の新卒でしたが、実質的には学生時代から社員のような状態でした。
最初の会社での仕事は、人材紹介会社と企業をマッチングさせるサービスの営業です。求人開拓の営業や人材紹介会社向けの営業など、BtoBの営業経験を積みました。しかし、リーマンショックの影響で景気が急激に悪化してしまったんです。自分がどれだけ頑張っても売上が下がっていく状況に直面し……。これが私にとって最初の試練でした。
その後、より安定した大きな企業で働きたいという思いから、アリババの日本法人に転職。ここでは日本の製造業や卸売業、中小企業に対して、Alibaba.comというグローバルなBtoBマッチングプラットフォームへの出店支援を行っていました。
ーーアリババでの経験は小林さんのキャリアにとって重要だったそうですね。
そうですね。アリババでの経験はキャリアにおける大きな分岐点でした。当時の中国では、国土が広大なため、インサイドセールスとフィールドセールスを分けた営業モデル、今でいう「The Model」が既に確立されていたんです。これはインサイドセールスがアポイントを取り、各拠点の営業担当者が訪問してクロージングする仕組みです。
2010年頃から、このいわば「中国版The Model」に触れる機会を得ることができました。現在のSaaSビジネスで一般的な営業モデルに早い段階で触れられたことは、大きな財産ですね。
自社プロダクト開発から中小企業支援へ。アリババからユーティルまでの軌跡

ーーアリババからクックパッドへ転職されたきっかけを伺えますか?
アリババは中国の会社であるため、日本法人は機能的な一部分に過ぎませんでした。開発は全て中国で行われていたので、日本のお客様からのプロダクトに関する要望や改善点をいただいても、それを反映することができない状況でした。
そこで「自分でプロダクトを作れる環境で働きたい」と考え、当時新規事業開発に注力していたクックパッドに入社しました。クックパッドでは、新規事業開発として自社のデータ資産を活用したアドネットワークの構築を担当することに。当時ネイティブアドが流行り始めた時期で、レシピのフォーマットに沿った広告商品を開発し、広告の仕組みを作りました。
ーーその後、Onionという会社を創業されたそうですね。
クックパッドでは残念ながら、経営陣の交代による組織再編があり、私が開発した広告商品も停止されることになりました。「それならば自分でやった方がいい」と思い、以前から知り合いだった人物と共に2017年頃にOnionを創業しました。
当時、SaaSビジネスが爆発的に流行りそうな雰囲気があり、私たちもBtoB向けのサービスを立ち上げようと考えたのです。徹底的に欧米のセールステック市場を調査し、日本にはまだない領域のSaaSを開発しました。
事業は順調に成長し、ARRベースで2〜3億円まで売上を伸ばしていきましたが、開発チームの課題でプロダクトの品質維持が難しくなり、売上が急激に下がってしまいました。組織再編を行い、最終的に2020年末に私自身も会社を去ることになりました。
ーーOnion退任後はどのような活動をされていたのでしょうか?
Onion退任後は、フリーランスとして様々な会社の仕事を手伝いながら、営業代行会社を立ち上げるなど活動していました。2021年から2022年の約2年間は、次の創業のネタを探しつつ、営業代行やコンサルティングで生計を立てていましたね。
しかし、自分一人で考え続けても新しいテーマが見つからないと感じ、「バリバリの上司の下で働くことで新しい視点を得られるのではないか」と考えるようになりました。そこでココナラに入社し、ビジネス統括部で法人向けサービスの立ち上げを担当しました。
ココナラでは非常に優秀な上司の下で多くを学びましたが、再び独立してSpicetechという会社を立ち上げました。EC事業者向けのSaaSプロダクトを開発していましたが、テストマーケティングの結果があまり芳しくなく、方向転換を考えていた時に、ユーティルの代表である岩田さんに出会い、「一緒にやろう」とお誘いをいただいたのです。
決め手は、代表の人柄と、ビジョンへの共感

ーーそこからユーティルグループにジョインしたと伺っています。決め手を教えてください。
ユーティルという会社は以前から知っていて、「伸びている」という話も聞いていましたし、単なる転職ではなくM&Aという形でのジョインだったことが大きなポイントでしたね。当時は自分の会社であるSpicetechを立ち上げたばかりで、事業に思い入れもありました。そんな中、岩田さんから「会社ごと買収するから一緒にやろう」と言っていただけたことが、決断の後押しになりました。
ーー岩田さんの掲げるビジョンにも共感されたそうですね。
そうですね。私は大きなビジョンを見つけるのが苦手なタイプでした。一方、岩田さんは「日本中の中小企業のポテンシャルを開放する」という大きなビジョンを掲げていて、感銘を受けましたね。
実際に自分が創業者として会社を経営して気づいたのですが、事業を立ち上げ、伸ばしていこうと思っている経営者たちは本当に素晴らしいと思います。日本には数多くの中小企業があり、それぞれが課題を抱えてチャレンジしています。そういった企業を支援するという方向性に大きな魅力を感じました。
BPaaSで変える、中小企業の未来

ーー現在率いているできるくん事業について教えてください。
できるくんでは中小企業向けに、BPaaS(Business Process as a Service)という特定の業務プロセスそのものを外部へアウトソーシングするサービスを提供しています。2016年頃からSaaSブームが来て、中小企業向けのSaaSもたくさん生まれました。
私自身もセールステックのSaaSを開発していましたが、中小企業がSaaSを導入しても使い手のリテラシーやリソース不足の問題で、十分に活用されないケースが多々ありました。そのため、現在のSaaS企業はミッドマーケット以上の企業をターゲットにするケースが主流になっています。
一方、BPaaSは、中小企業に対するデジタル化支援と非常に相性が良い。私たちがBPO事業者としてデジタルツールを活用しながら、中小企業の課題を業務として請け負うことで、中小企業は今まで恩恵を受けられなかったデジタル化の恩恵を受けることができるのです。
ーー普段対峙する中小企業はどのような課題を抱えていることが多いですか?
中小企業の課題は非常にシンプルで、主に「売上を伸ばせない」「採用できない」という2点に集約されます。これは中小企業庁が発表しているデータでも明らかで、この2つの理由で倒産していく会社が最も多いのです。
できるくんでは、まずホームページを低価格で提供し、創業間もない会社のデジタルプレゼンスを構築します。そして、ホームページ制作後の集客支援や採用支援などのサービスをワンストップで提供することで、中小企業の成長を支援しています。
ー−ホームページ制作市場におけるできるくんの優位性についてどうお考えですか?
ホームページ制作の領域は、差別化が難しい市場です。日本には何百何千というホームページ制作会社があり、「安い」「早い」「品質が良い」といった点はどの会社も掲げることができます。
顧客から見た最大の違いは、おそらく入り口、つまり営業だと思います。特に創業間もない企業にとって、初めてのホームページ制作は大きな投資です。「この会社に発注したら安心」と思っていただける営業力、人間力が重要になると考えています。
ーーできるくんの受注率は全体で35%程度と比較的高いと思うのですが、その理由はどこにあると思いますか?
一つはマーケットの変化です。従来、ホームページ制作費用は平均で80万円程度かかっていました。しかし、AIの発展やWixなどのCMSの普及により、制作原価が大幅に下がってきています。そのため、これまで高額な費用を理由にホームページ制作を諦めていた創業間もない企業でも、手の届く価格でホームページを持てるようになってきました。
このマーケット変化に対応し、低価格でクオリティの高いホームページを提供することで、多くのリードを獲得できています。特に創業間もない企業は、「安さ」と「早さ」を重視していて、できるくんのサービスと相性が抜群です。
さらに、他社との大きな違いとして、ホームページ制作後のサポートも挙げられます。多くの制作会社は納品で終わりですが、私たちは集客支援や採用支援まで一貫してサポートします。特に創業間もない小規模企業に対して、こうした伴走型のサービスを提供している会社は少ないと思います。
受注率60%の型。トップセールスが仕掛けた組織改革

ーーできるくんの事業体制はどのように構築されてきましたか?
私がジョインした当初は、営業1名、商品開発1名、制作の業務委託スタッフ1名、インサイドセールス4名という体制でスタートしました。まず最初に取り組んだのは、制作のクオリティ向上です。お客様に「Wow!」と思わせる体験を提供するため、高品質なサンプルサイトを約10個作り、提案の武器にしました。
その結果、受注率が向上し、私が着任する前は月に10件未満だった受注数が、着任後は20件、その翌月には38件と倍々で増えていきました。すると今度は制作のリソースが追いつかなくなり、一度営業を抑制して制作チームの強化に力を入れました。
ーーそれはすごいですね!他に、受注率を高めるために工夫されたことはありますか?
自ら現場に出て、メンバーと同じくらいの件数の商談を実施しました。「自分が最も高い受注率を達成できなければならない」と考え、様々な営業手法を試行錯誤したのです。結果的に私の受注率は60%程度まで上がり、その成功事例をチーム全体に展開していったことが大きかったですね。
具体的にはアリババ時代の経験を活かし、トップセールスのスクリプトや資料、各スライドのトーク内容などをすべて「型」として共有し、チーム全体で同じ手法を実践しました。最初はメンバーの受注率平均が15%程度でしたが、この取り組みによって30%以上まで向上させることができたのです。
ただし、同じスクリプトを使うことで営業担当者に窮屈さを感じさせないように工夫も必要でした。そこでメンバーが受注した時は大いに賞賛し、チーム内のグルーブ感を醸成するなど、組織としての一体感も大切にしています。
ーーマネジメントで意識していることはありますか?
私が特に意識しているのは、自分の喜怒哀楽の表現です。どういうところで喜び、どういうところで怒り、どういうことで楽しいと思うのかを、オーバーに表現するようにしています。さらに、自分の感情の割合も意識的にコントロールしています。
具体的には、喜びや楽しさといったポジティブな感情を全体の7割程度に保ち、厳しさや緊張感を3割程度にしています。楽しいだけではチームが弛緩してしまうので、定例会議などでは締める意味でも厳しいことを言うこともあります。この強弱のバランスがチームの健全な成長に繋がると考えています。
ーーできるくんのサービスによる成功事例があれば伺いたいです。
モデルのウォーキング講座を運営しているお客様の例が印象的です。まだホームページは導入段階でしたが、急遽資金が必要になり、すぐに数名集客する必要がありました。当社の担当者がInstagramの広告を5万円ほどで発注したところ、3名の集客に成功し、1件の契約を獲得できました。お客様から「生き延びた」という言葉をいただいたときは本当に嬉しかったですね。
このように中小企業の経営者と直接関わり、その課題解決を支援できることは大きなやりがいです。中小企業の社長との接触数が多いことは、BtoB営業の大きなメリットの一つ。意思決定が早いことに加え、様々な経営者との会話から多くを学ぶことができます。例えば、高所作業の専門家として活躍している経営者との出会いは非常に印象的でした。自分の専門分野で独自のノウハウを持ち、他の人がやりたがらない仕事で成功している……そういった経営者との出会いは刺激になります。
「成長」をキーワードに、日本全体の底上げを

ーーできるくんの今後の展望を教えてください。
まずはホームページ制作で多くの顧客を獲得します。そして、その顧客に対して集客支援や採用支援といった周辺領域のBPaaSサービスをクロスセルしていく。最終的には、蓄積されたデータを活用した新たなサービスを開発し、顧客やその他の企業にも価値提供できるよう拡大していきたいと考えています。
BPaaSの面白い点は、SaaSプロダクトと比較して開発サイクルが非常に速いことです。SaaSはエンジニアが開発し、リリースまでに時間がかかりますが、BPaaSは既存のSaaSやAIを活用してサービスを提供するため、リリースまでの期間が短く、課題が見つかった際も迅速に修正できます。
現在、できるくんはノーコードで多くのサービスを開発しており、ビジネスサイドだけの意思決定でPDCAを回せる点も大きな強みです。これにより、エンジニアリソースに依存せず、迅速にサービス拡充が可能になっています。
ーー今後、どのような人材とともに成長していきたいですか?
求めているのは、「成長」意欲をお持ちの方です。そのキーワードの「成長」とは、事業の成長、組織としての成長、自分自身の成長、お客様のサービス成長など、いずれの観点であれ「成長」に価値を見出しアンテナが立っている候補者様との相性が良いと感じています。特に、今後の展開を考えると、機会の拡がりとともに若くポテンシャルがあり勢いのある人材を積極的に採用していきたいと思っています。
また、ユーティルグループの特徴として、ベンチャー・スタートアップでありながら、既存事業による安定した収益基盤があることが挙げられます。つまり、チャレンジングな環境でありながらも、必要な投資をしっかりと行える財務状況があります。成長意欲のある人材にとって、非常に魅力的な環境だと思います。私たちと一緒に中小企業のデジタル化を支援し、日本全体の底上げに貢献しましょう!
中核を担う方を募集中です!